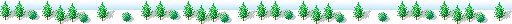
第4回 定例会 議事録
日 時:2000年8月26日 13:30〜16:30
場 所:関口教会会議室
参加者:14家族、医療関係者3名、ボランティア
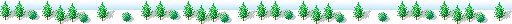
- フリーディスカッション:自己紹介を兼ねて
関西支部の立ち上げは秋に本格化との報告あり
- 「排痰について」の講義と実演:東京女子医大安達みちる先生
排痰の具体的な方法‥‥実演をしながら
(1)咳を強くする‥‥いっぱい吐いて一気に吐く
本人を仰向けに寝かせ頭の側に位置し、呼気にあわせて両手の手のひらで胸を押す(押す方向は臍の背中側をイメージするとよい)。すると自然に吸気が強くなり、肺に多くの空気が入るため咳が強くなる。もし本人が咳をできるのであれば、何度か呼気を助け、合図をして咳を介助する。普段から咳の練習をしておくとよい。
(2)重力の利用‥‥痰の移動を促す
痰がどこにあるのか確認できる場合には姿勢を換えて(1)を行う(右肺に痰がある場合は右側を上にして横たわる)。聴診器がなくても手のひらを胸に当てて、振動があるのを確認できることもある(わからない場合は仰向けで可)。
痰が太い気道に出てくるとゼイゼイ音となるので、(1)の姿勢で肺痰を促す。その際に布団や枕を利用し頭部を少し低くすると肺痰が容易となる。但し長時間頭部を低くするのは不可。
(3)エアエントリー‥‥吸気を多くする
(1)のとおり呼気を多くすれば吸気も多くなる。吸気が多ければ肺痰は容易になる。
(4)振動‥‥痰を流動化する
振動を加えることにより排痰を促す。タッピング(手のひらで叩く)のも有効だが、呼気に合わせて軽く叩くのがよい。
(5)痰の性状を変える‥‥痰を流動化する
水分の補給や加湿で痰を流動化する。
・一番大切なのは風邪を引かないこと。ex)手洗い、うがいの励行
・疲労は禁物、咳は体力を消耗するので注意。
- 第42回小児神経学会報告:東京女子医大斎藤先生
今回はSMAに関するテーマがかなり多くあった。
中でも注目は台湾の鐘育志先生らによるSMAモデル動物の開発で、これは今後のSMA研究の大きな一歩となる可能性がある。
以上

![]()
![]()