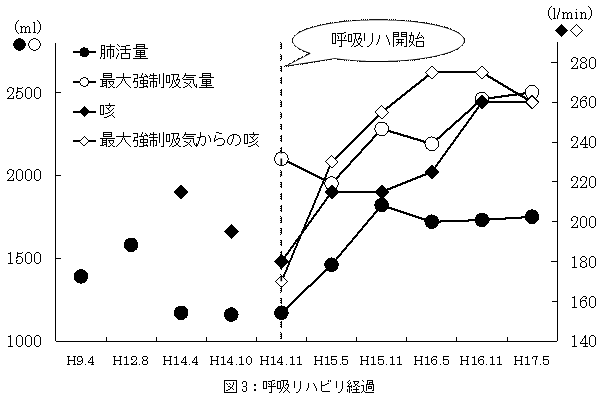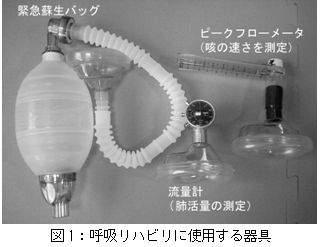【呼吸リハビリの進め方】
排痰機能の評価は、ピークフローメータ(図1)を使用し咳をしたときの速さを測定します。一般的に、その値が270 l/min以下になると風邪をひいたときなど粘稠な痰の排出が困難になるといわれています。さらに160
l/min以下になると、日常的に気道内の分泌物の排出が困難になるとされています。したがってリハビリとしては、咳の速さが270 l/minを上回るように練習します。しかし、リハビリをすれば咳の機能が飛躍的に伸びるわけではありません。ここでは、当事者の呼吸機能にあった排痰手段を選択すると言ったほうが正確かもしれません。咳の方法としては大きく分けて4つあります。①自力での咳、②緊急蘇生バッグ(図1)を用い強制的に息を吸い込ませた状態(最大強制吸気)からの自力での咳、③自力で吸った状態から介助者に胸を押してもらい咳を介助してもらう方法、④最大強制吸気から介助者に胸を押してもらう咳の介助をする方法です。また、それでも排痰困難となる場合を想定し、カフマシーン(痰を喀出させる機械:図2)の練習をあらかじめしておく場合もあります。
①の方法で270 l/min以上の場合は経過観察で良いと思います。したがって、当院では咳の速さが270 l/min以下となると緊急蘇生バッグを用いた呼吸リハビリを実施することとしています。また先行研究では、肺活量を同年齢で同じ体格の健常者と比較した場合(%VCと言われている)、40%以下になると咳の能力も有効的な数値を下回る傾向にあると報告されています。したがって、肺活量比率が40%程度になっても呼吸リハを開始しています。そのほか、緊急蘇生バッグを用いて強制的に吸気させることは、咳の練習だけではなく、肺の弾性を保つ目的や咽頭機能の維持の目的もあります。
【はじめに】
先日,当院に通院されている方の親御さんより、神経筋疾患の当事者の中には「リハビリって効果があるの?」という疑問をもたれている方や、リハビリしたって変わらないのだからしていないという方がいらっしゃるとお聞きしました。なかでも「呼吸リハビリって効果があるの?」「いつ始めればいいの?」「どんなことをするの?」といった疑問があるようです。そこで今回は、呼吸リハビリでどのようなことを行うのか、いつから始めればいいのか、実際効果はあるのかについて実例を挙げて述べたいと思います。
【呼吸リハビリの目的】
神経筋疾患では呼吸をするために必要な筋も低下してしまいます。そうなると上気道感染時(たとえば風邪をひいた時)などに痰が詰まりやすくなり、肺炎となる危険性が高くなってしまいます。したがって、神経筋疾患における呼吸リハビリの主な目的は、有効な排痰機能または手段の維持です。また2つ目の目的には、強郭や肺自体の弾性力(やわらかさ)の維持があります。神経筋疾患では、呼吸筋力が低下することにより強郭の運動が制限され強郭が硬くなってしまいます。さらに十分肺の隅々にまで空気が送り込まれず、肺自体が硬くなってしまいます。